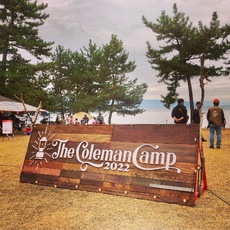2017年05月11日
コットンテントのカビ取り作業。
GWキャンプで張ったテントはブログでも頻繁に登場するコールマンのオアシスDX2で、90年代に販売されていた貴重な、コールマンにのめり込むきっかけにもなったテントです。
前回使用したのは2016年の8月のキャンプ。
約9か月振りに張ったオアシスDX2の天井にはカビが発生していたのです。

オアシステントの庇の先はポールを差し込む様になっていて、頑丈に作られています。
その分、厚みがあり乾きにくい箇所でもあります。
しっかり乾かして畳んだつもりが、庇の先が湿っていた様です。
畳んだ時に庇の先が重なる天井部分に黒カビが発生していました。
直径20cm程度もある大型のものです。

大事に使ってきたテントにカビ・・・、しかも天井ですから寝る時に目に飛び込んできます。
貴重なテントを譲ってくれた師にも申し訳ない気持ちでいっぱいになります。
GWキャンプ初日にカビ取り剤をAmazonで注文し、帰宅日の夜に届く様に日時指定しました。
キャンプから帰ってきた翌日、早速カビ取り作業にチャレンジです。

庭にテントを広げて作業の準備をします。

作業前のカビの状態。
外から見てもしっかりカビが分かります。
(日陰になっていてわかりにくいですが、カビカビです。)

内側から見ると光に照らされて真っ黒なカビが悲しいぐらいにはっきり見えます。
この時点でどこまでカビを落とせるのか、不安な気分でいっぱいです。

カビ取り剤を染み込ませて作業しますが、他の生地に影響が出ない様に、大きなビニールに包んだ段ボールをカビの下に当てて作業します。
生地やフロアーに必要以上にカビ取り剤を付けずに作業できる様にしました。

カビ取り剤を吹き付け、カビの箇所に浸透する様になじませます。
テントは撥水加工されていますし、生地も厚いので吹き付けただけではカビにまでカビ取り剤は届きません。
手ごろな空き瓶を使ってトントン叩きながら裏側に染みるように作業しました。

表からカビ取り剤を吹き付けトントン、裏面までしっかりとカビ取り剤が浸透したらしばらく放置。
乾いてきたら同じようにカビの部分にスプレーし、トントンと馴染ませます。
しばらくするとカビが薄くなっていきます。
やりすぎて生地を傷めない様に様子を見ながら注意を払い作業します。

1時間半程度でカビはほぼ目立たない程度にまで消えました。
生成りのコットン生地ですが、カビの発生していた箇所は白っぽくなってしまいましたが、黒カビが発生した状態に比べたら気になりません。
濡れているので他の部分との差ははっきりし過ぎていますが、乾けば多少は状態はよくなると自分を励ましていました。

カビが消えてきたらすすぎ作業に入ります。
”乾燥すればカビ取り剤は無害になる”と説明文に記載されていますが、テントは雨に濡れることがあります。
濡れた際に有害成分が復活してテントにダメージを引き起こさないとも限りません。
カビ取り剤を染み込ませた箇所の下にバケツを入れ、ぬるま湯に浸してもみ洗いをしてカビ取り剤を抜きます。
お湯を2回交換し、そのあとはしばらくお湯に浸した状態にしてカビ取り剤を抜きます。

濯ぎが終わったら、濡れた部位をバスタオルで挟み、足踏みして水気をバスタオルに吸わせます。

あとは、乾燥するまで放置。
朝の8時半頃に始めたカビ取り作業はお昼頃には乾燥まで完了させることができました。
カビ取り作業を終え、天井部分は落ち込んだ気持ちが和らぐところまでリカバリーさせることができました。

↑外からみたところ。
言われなければ気付かない程度だと自分に言い聞かせます。

↑内側から覗いた状態。
カビのあった場所はカビ抜きで漂白されていますが、知らない人がみたら気に留まらない程度(?)になりました。
大事なテントに大きなカビを発生させてしまいましたが、なんとかリカバリーすることができて一安心です。
今後はカビが発生しない様にいままで以上に注意を払います。
皆さんも十分にお気を付けください。
Fin
前回使用したのは2016年の8月のキャンプ。
約9か月振りに張ったオアシスDX2の天井にはカビが発生していたのです。

オアシステントの庇の先はポールを差し込む様になっていて、頑丈に作られています。
その分、厚みがあり乾きにくい箇所でもあります。
しっかり乾かして畳んだつもりが、庇の先が湿っていた様です。
畳んだ時に庇の先が重なる天井部分に黒カビが発生していました。
直径20cm程度もある大型のものです。

大事に使ってきたテントにカビ・・・、しかも天井ですから寝る時に目に飛び込んできます。
貴重なテントを譲ってくれた師にも申し訳ない気持ちでいっぱいになります。
GWキャンプ初日にカビ取り剤をAmazonで注文し、帰宅日の夜に届く様に日時指定しました。
キャンプから帰ってきた翌日、早速カビ取り作業にチャレンジです。

庭にテントを広げて作業の準備をします。

作業前のカビの状態。
外から見てもしっかりカビが分かります。
(日陰になっていてわかりにくいですが、カビカビです。)

内側から見ると光に照らされて真っ黒なカビが悲しいぐらいにはっきり見えます。
この時点でどこまでカビを落とせるのか、不安な気分でいっぱいです。

カビ取り剤を染み込ませて作業しますが、他の生地に影響が出ない様に、大きなビニールに包んだ段ボールをカビの下に当てて作業します。
生地やフロアーに必要以上にカビ取り剤を付けずに作業できる様にしました。

カビ取り剤を吹き付け、カビの箇所に浸透する様になじませます。
テントは撥水加工されていますし、生地も厚いので吹き付けただけではカビにまでカビ取り剤は届きません。
手ごろな空き瓶を使ってトントン叩きながら裏側に染みるように作業しました。

表からカビ取り剤を吹き付けトントン、裏面までしっかりとカビ取り剤が浸透したらしばらく放置。
乾いてきたら同じようにカビの部分にスプレーし、トントンと馴染ませます。
しばらくするとカビが薄くなっていきます。
やりすぎて生地を傷めない様に様子を見ながら注意を払い作業します。

1時間半程度でカビはほぼ目立たない程度にまで消えました。
生成りのコットン生地ですが、カビの発生していた箇所は白っぽくなってしまいましたが、黒カビが発生した状態に比べたら気になりません。
濡れているので他の部分との差ははっきりし過ぎていますが、乾けば多少は状態はよくなると自分を励ましていました。

カビが消えてきたらすすぎ作業に入ります。
”乾燥すればカビ取り剤は無害になる”と説明文に記載されていますが、テントは雨に濡れることがあります。
濡れた際に有害成分が復活してテントにダメージを引き起こさないとも限りません。
カビ取り剤を染み込ませた箇所の下にバケツを入れ、ぬるま湯に浸してもみ洗いをしてカビ取り剤を抜きます。
お湯を2回交換し、そのあとはしばらくお湯に浸した状態にしてカビ取り剤を抜きます。

濯ぎが終わったら、濡れた部位をバスタオルで挟み、足踏みして水気をバスタオルに吸わせます。

あとは、乾燥するまで放置。
朝の8時半頃に始めたカビ取り作業はお昼頃には乾燥まで完了させることができました。
カビ取り作業を終え、天井部分は落ち込んだ気持ちが和らぐところまでリカバリーさせることができました。

↑外からみたところ。
言われなければ気付かない程度だと自分に言い聞かせます。

↑内側から覗いた状態。
カビのあった場所はカビ抜きで漂白されていますが、知らない人がみたら気に留まらない程度(?)になりました。
大事なテントに大きなカビを発生させてしまいましたが、なんとかリカバリーすることができて一安心です。
今後はカビが発生しない様にいままで以上に注意を払います。
皆さんも十分にお気を付けください。
Fin
スノーピーク 火炎 ストーブ サカン(Kaen Stove Sakan)。
マルシャル ビクトリア5 (Marechal Victoria 5) 入手
バイヤー ムースヘッドチェアのカラバス化。
モスキートランタン購入。
ソロキャン用にクーラーボックス新調。
バッテリー内蔵ファンで暑さ対策。
マルシャル ビクトリア5 (Marechal Victoria 5) 入手
バイヤー ムースヘッドチェアのカラバス化。
モスキートランタン購入。
ソロキャン用にクーラーボックス新調。
バッテリー内蔵ファンで暑さ対策。
この記事へのコメント
コットンテントはやはり大変なんですねー
いつか持ちたいとは思いつつも手入れし切れるか不安が残ります。
・・・といっても他に欲しいものがあるので最後の大物として残ったままですが。。。
いつか持ちたいとは思いつつも手入れし切れるか不安が残ります。
・・・といっても他に欲しいものがあるので最後の大物として残ったままですが。。。
Posted by 吹雪。 at 2017年05月11日 06:48
◆吹雪さん
コットンテントのメンテは乾かして仕舞えばよいだけと言いますし、言っていましたが今回の様な事になってしまいました。
不幸中の幸いは生成りの生地部分にカビが発生していた事でした。
色の付いた生地だと色落ちは避けられないのかもしれません。
快適さなどを考えるとコットンテントは良いですが、やはり化繊生地のテントに比べると扱いはデリケートですね。
それも含めて楽しむ時期がくるとよいですね!
^_^
コットンテントのメンテは乾かして仕舞えばよいだけと言いますし、言っていましたが今回の様な事になってしまいました。
不幸中の幸いは生成りの生地部分にカビが発生していた事でした。
色の付いた生地だと色落ちは避けられないのかもしれません。
快適さなどを考えるとコットンテントは良いですが、やはり化繊生地のテントに比べると扱いはデリケートですね。
それも含めて楽しむ時期がくるとよいですね!
^_^
Posted by F-15 at 2017年05月11日 07:09
at 2017年05月11日 07:09
 at 2017年05月11日 07:09
at 2017年05月11日 07:09大切に使っていてもいつかはそんな日が来るような気がします。
とっても参考になる記事でした。
それにしてもホント目立たなくなるんですね!!
とっても参考になる記事でした。
それにしてもホント目立たなくなるんですね!!
Posted by いっけ at 2017年05月11日 08:51
at 2017年05月11日 08:51
 at 2017年05月11日 08:51
at 2017年05月11日 08:51◆いっけさん
大事に使っていてもこんな事になっちゃいました。
カビが発生する前のオアシスを張ったキャンプではタープを被せていたのですが、後ろ側の庇の先がタープからはみ出していて、はみ出した側の庇の先が湿っていた様です。
今後は庇の先が乾いていることを確認してから畳もうと思います。
いっけさんもオアシスを畳む際には庇の先部分にはご注意を!
( ´∀`)b
大事に使っていてもこんな事になっちゃいました。
カビが発生する前のオアシスを張ったキャンプではタープを被せていたのですが、後ろ側の庇の先がタープからはみ出していて、はみ出した側の庇の先が湿っていた様です。
今後は庇の先が乾いていることを確認してから畳もうと思います。
いっけさんもオアシスを畳む際には庇の先部分にはご注意を!
( ´∀`)b
Posted by F-15 at 2017年05月11日 09:10
at 2017年05月11日 09:10
 at 2017年05月11日 09:10
at 2017年05月11日 09:10こんにちは~。
うちの化繊のテントでも、ちょっとかび臭いときがありますが(・Θ・;)アセアセ。
コットン幕だと、カビはキビシイですよね。
でも、キレイにリカバリー出来た様でなによりです。
うちもそろそろテントキレイにしないといけないな~って思いながら、なかなか腰があがりませんヽ(´∞`)ノ アウアウ。
うちの化繊のテントでも、ちょっとかび臭いときがありますが(・Θ・;)アセアセ。
コットン幕だと、カビはキビシイですよね。
でも、キレイにリカバリー出来た様でなによりです。
うちもそろそろテントキレイにしないといけないな~って思いながら、なかなか腰があがりませんヽ(´∞`)ノ アウアウ。
Posted by ユイマーる at 2017年05月12日 08:30
at 2017年05月12日 08:30
 at 2017年05月12日 08:30
at 2017年05月12日 08:30◆ユイマーるさん
こんにちは。
今回は大事なコットンテントにカビを育ててしまいました。
使っているとこんなこともあると理解できていても、ショックでした。
化繊幕はコットンに比べれば扱いは楽ですが、ノーケアで使い続けられるものではないですもんね。
大切なテント、しっかりとケアしてあげなきゃですね!
(≧∀≦)
こんにちは。
今回は大事なコットンテントにカビを育ててしまいました。
使っているとこんなこともあると理解できていても、ショックでした。
化繊幕はコットンに比べれば扱いは楽ですが、ノーケアで使い続けられるものではないですもんね。
大切なテント、しっかりとケアしてあげなきゃですね!
(≧∀≦)
Posted by F-15 at 2017年05月12日 09:24
at 2017年05月12日 09:24
 at 2017年05月12日 09:24
at 2017年05月12日 09:24